丹沢 早戸川 中ノ沢
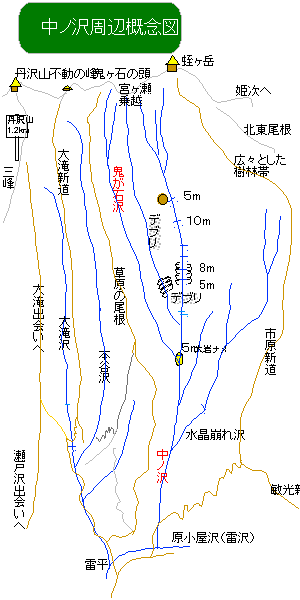
最近、こんなこと考える。
もう何回くらい自転車で山に行けるのかなって
体力的にきついのは当然として、自転車そのものがかなり傷んできているのが痛い。
ホントはまだ大丈夫なつもりなのだが、トー・トラップは一時代前のやつなので壊れた場合の補充パーツをもうお店では売ってない。
最新のにすればいいじゃんというのは確かにそうだが、旧式のバンドで固定するタイプは靴が普通のが使えるのが便利なのだ。
最近のは靴底で引っかけるタイプだが、これだと自転車乗っている間は良いが、山の中では靴底が大切なのだ。最近のだと山歩き用を別に持って行かなくてはならないという不都合があって良くない。
タイヤだって最近のタイプに替えればそこらのお店で買えるし、そもそもパンクには強くなって交換の回数が減るはずだが、それには車輪を替えなくてはならないが、いまさらね。
だから乗る意欲はあっても走れる自転車では無くなりつつあって、もうそんなに長くは続きそうもない。
なんかいいわけ 言っているよね
このように最近、ちょっと弱気だと思う。62にして5月病でもないはずなのに 若い頃に掛かったのが慢性化して治癒してないようだ。なんとかしなくっては
今日は自転車で行く。残り回数は百ウン十−1回となった。
道路大丈夫だろうか。
パンク誘発する小石がたくさん路上に散らばっていないか。それが気がかりだったが、概ね問題はない。
早戸川には渓流釣りの人が数多く立ち、遊漁券を確認するため双眼鏡を片手にして林道を行ったり来たり往来する軽四トラックもあったりして、思っていたよりも川沿いにはずっと人が多い。
抑え気味にペダルを踏んできたので、三日月橋から傾斜増す登りも、あたりの様子を見ながら済ますことが出来たように思える。
堤防から落ちる水の音が響き聞こえる魚止橋に自転車を止めて歩く。
伝導沢を渡ってP776mを経由して造林小屋に出る元々の道は踏み跡薄くなる一方で、
他方、沢を渡って直ぐ右手の小沢に沿って行く方が踏み跡が濃くなっている。今までは旧の方が使われていたトレランコースも今年はこちらに設定されたらしい。
造林小屋は1mにつき8cm位の角度で小屋の後ろに向かって傾いている。前回見た時には開閉ドアを押し上げれば枠に収まったはずなのに、何とかピッタシ閉じようと押し上げ入れようと思うが今回はぜんぜんだめだ。大雪時の屋上の重みが柱にかかって傾きが増したのだろう。使われなくなった小屋はいつか壊れるが、それは遠くないように思う。
 雷淵上の徒渉点
橋はないが飛び石するも徒渉するも自在である
なにも不安定な丸太に頼ること無し
雷淵上の徒渉点
橋はないが飛び石するも徒渉するも自在である
なにも不安定な丸太に頼ること無し
壊れかかっているのは造林小屋だけではなく、雷淵への水平経路も似た状態だ。
対岸に瀬戸沢太礼の沢出会いが見えてくるあたりで、経路の何ヶ所かを橋で岩場突端部を通過することになる。その桟橋は以前よりずいぶんと傷んでいたが、そのうちの最急傾斜部、途中に折れ曲がりのあるのが落ちていた。曲がり部の橋脚が構造的に弱いから一番最初に壊れたものと知ったかぶるが、
この桟橋が無いと、この岩場の通過は面倒である。
橋の替わりにロープが垂らされているが、垂直な岩場であり、着地する斜面も急斜面中なので腕力に自信がないと、このロープは使えないだろう。年寄りや山道に慣れてない女性ならロープで体を確保して安心感を保たせないと、この岩場の登下降するのが困難だろう。
危険なので回り道がそのうちに出来るかなとは思うが、周囲は露岩が出ている場所なので、かなりの遠回りになる可能性がある。それにこの橋だけではなく、前後の桟橋も似たような状態である。大雪の重みで壊れるならまだ救いがあるが、誰かがいつか通行中に、ぼそっと落ちるとなる場合も想定できる。
日本の滝百選に選ばれた神奈川県に二つしかない滝の見物用径路なのだ。
そこがこんな状態あるとは知らずにやってくる人もいるだろうし、その中には山道を歩き慣れてない人もいるだろう。
今の状態なら、経路の危険をより強く警告する必要があるように思うが、神奈川県の保全センターも、神奈川県企業局も、それぞれ業務の管轄外として事故の起こるまで何の処置もされないのかね。事故が発生した場合、相模原市はこれで責任果たしていると言えるのかな。
雷淵上徒渉点の丸太は流れたままである。
水に入るなり、飛び石するなり各自が好きに渡ればよい。
雷平を通過し原小屋沢方向に入って直ぐに対岸に渡る。そこには中ノ沢出会いへの作業路が着いているのである。黄色ペグが点々と連続して埋まっているが、道は薄く踏み跡道とでも云うにも足りないくらいになっていたが藪ではないから歩くに支障ない。
中ノ沢
支流の沢は登っている。蛭ヶ岳からの降りで本流を下ったこともある。
でも下から上までを素直に登ったことはない。大きな滝は無いことになっているが、知っているようで、実際は知らない沢なのだ。今日はそこを歩くことにしてる。
 中ノ沢に入る。明るく広い沢
最初は良さげだが、最後までこの雰囲気は変わらない。
よって大滝も危険な棚もない
中ノ沢に入る。明るく広い沢
最初は良さげだが、最後までこの雰囲気は変わらない。
よって大滝も危険な棚もない
入って直ぐは石が不規則に転がるがらがら沢だ。いやいや入り口だけでなく、沢の最後に至るまでずっと石が転がっていて大きな滝はない沢だ。
出会いが見える位置の左岸から杉の植林帯の下縁を通り、市原新道に合流する作業路があったはずで、その道の入り口付近には赤テープなどの目印があったように記憶しているが、その目印が探せなかった。
目を付けていても、見えるのは人の欲くらいしか感じされないマシラの節穴の目で見逃した可能性があるが、ここからの利用者少なく、しるしが薄くなっているのはおそらく確実である。
がらがらの道を行く。
左岸から石が押し出し堆積している水晶沢出会いを過ぎる。
至る所で倒木ががらがらの石の上に覆い被さってくる。今冬の雪によって倒されたのだろう。これを避けるための枝を押しのけ、下をくぐり、上に跨いで通過するのが、そこで踏む岩や石なんかも残雪から出てきたばかりで座りが定まっていない。一つ一つがグラグラしあ重なった石を踏もうなら、まず確実に崩れる。だから見た目以上に面倒なのである。そんなだから思っているスピード感から遠く、ピッチは上がらず、それに緊張感を呼び戻す滝も難場もなく、のんびり感ただよう歩き方になってしまう。
それも悪くないかな
雪の原になる。雪田といっても良いかもね。
石の原よりは雪の原の方が幾らか歩き易くなるか。
だが、腐った雪は思ったよりも滑り、雪に沈んで、そのくせ傾斜部では腐った雪が蹴り足を滑らせて歩きにくい。
雪は体を支えるほどに丈夫だろうか。平均面より窪んだところは下が融けている証拠だ。そういうのは避けようとすると沢の中央から左右のどちらかによって靴のエッジを利かせるようにした登りになる。
 雪田は融けて崩落直前だ
雪の上を歩くなら観察うまく正しく選定して歩く必要がある
そうでないと危険となる場合もある
雪田は融けて崩落直前だ
雪の上を歩くなら観察うまく正しく選定して歩く必要がある
そうでないと危険となる場合もある
 雪田を下から観察すれば
日の光りが雪面を突き刺すくらいに薄くなっているところだってある。
この画像雪面上からの楽さなら3mは落ちて十分危険地帯だぜ
雪田を下から観察すれば
日の光りが雪面を突き刺すくらいに薄くなっているところだってある。
この画像雪面上からの楽さなら3mは落ちて十分危険地帯だぜ
小滝に達する。右横から回ってパスする。
すぐ左に鬼ヶ石沢が合流してくる。この出会いからもう少しだけ奥に行ったところに乗越沢がある。
今日は中ノ沢を歩くと言ったが、蛭ヶ岳の山頂にまで行く予定はなく、鬼ヶ石から富士山を眺めればそれで十分だと思っていた。その場合には中ノ沢乗越沢が適している。
乗越沢。
出会いが滝状と書けば、そうとも言える程度の岩場だが、それ以外には岩場は無いはず。稜線直下の斜面が急だが、そこには少々古びていても虎ロープが設置されている。ここらで落ちた大戦中の航空機の後年での残骸捜索の時に設置されたものではないかと想定されるが、ここから過去に下降した二回ほどの機会にありがたく使わせてもらった記憶がある。
だから、今日はここに入ろうと思っていた。
入り口は明確にわかっていたはずだった。鬼ヶ石沢出会いからは百〜二百mくらいの距離しか離れていないと覚えている。
だが、入り口 見つけ損なった。入れなかった。
結果 中ノ沢本流を歩くことになった。
先ほどの小滝を超えたあたりから中ノ沢は大量の雪に覆われていて、ちっちゃな沢の入り口もその中に埋もれていて、分かりにくかったというのをこの見逃しの言い訳として、まずは書いておこうと思う。
 踏み抜いた
落ちたのが1mほどだから笑っていられるが
その瞬間には凍り付いたよ
踏み抜いた
落ちたのが1mほどだから笑っていられるが
その瞬間には凍り付いたよ
ここかな、
いや 違うんじゃないか、
それよりも傾斜度を増す腐り雪に靴を取られて嫌だね
そこらで拾った先のとがった木片をストック代わりにして登る。それに、融けた雪渓だ。いつ何時踏み抜くかわからない。最初の小滝の手前で雪渓の中に頭を除かせている露岩近くを通過しようとしたら「ズボッ」と雪が抜けた。広げた両手が雪の上に乗っかって足は宙ぶらりん状態で止まった。
その間から下を見ると少しで着地しそうな危険性のない状態だったが、もしも下が滝だったら、踏み抜きはぞっとするような思いとなっただろう。
踏み抜いたそこから抜け出るのだって面倒だ。回りは崩れるし、下に飛び降りるには下はゴツゴツしていて捻挫くらいは覚悟しなくちゃあと
そんな感じで歩いていたので、あるはず場所を見逃して行き過ぎてしまったのだろう。
雪田はずっと連続して続いているのではない。
急な場所では雪は切れる。狭い場所の急な所から雪が溶け、下には岩が見える。滝があるところである。それを登ろうと身構えた雪の上端が崩れるが、承知の上で準備しているので特に気にはしない。沢床から登り返す。
それにしても あの雪から三ヶ月が経過するとうのに、まだ雪が残っている。
日の当たる東面側でこんなだから、対面に当たる仏谷なんかはまだ一面の雪が上端部まで覆っているのではないだろうか。そこ行くには音久和で猟犬飼う人の家の前を通過しなくてはならなくて、俺にはそこが鬼門で通過できないアプローチだから出かけられない。だから蛭ヶ岳北面が今がどうなっているのかは興味津々だ。 でも忘れよう、そういうところは。
その小滝を抜けると上に滝が見えた。おおよそ10m程の滝だ。
下の右手から左上がりのクラックが滝の落ち口左に伸びていて、登るならここが一番楽そうだ。右手の露岩から幾筋もの湧水がはじけるように溢れ出る。そいつを飲む美味さと云ったらなんと書けば良いのだろう。
いざ・ではと登りだしたが、登れずに止めた。
岩には苔がびっしりと生えていて、それ自体は滑り止めになっているような感触だが、苔は岩のホールドも覆っていて掴みにくい。
そこの上に落ち口から岩肌を伝って流れる水がジクジクと垂れて落ちていて、ゆっくりとしか登れそうもないのに次の確かなホールドが手の中にないのだ。
取り付きからしてそうなのだから、滝の中央を左に横断する中間部のジクジクしたところで体を空間外に出さないと乗り切れそうもない所が、何か嫌らしいそうな感じがしたのだ。
湧き水飲む前の、簡単に登れそうな気分のままスッと登れば良かったのに、先では水がないかもと”ここで一口”と言って湧き水を飲んでいる間にその気分はどこかに行ってしまって登れなくなってしまったのだ。
湧水口の右側を8m登り、そこから左の落ち口に向かう岩場の間の砂場を横断して渡る。岩の上の薄い砂地を渡るときは、砂がこのまま崩れて落ちてしまうのでないかとハラハラドキドキするのがいつもだが、ここも同じだ。
 8m滝 傾斜は強くないが
濡れそうなのと左に移るところに確かなホールドがなさそうなので
右から巻いてしまいました。
以前、雪氷が着いていたときには登れていたのに
8m滝 傾斜は強くないが
濡れそうなのと左に移るところに確かなホールドがなさそうなので
右から巻いてしまいました。
以前、雪氷が着いていたときには登れていたのに
平板状の小滝を越えると、短い雪田を挟んで3mのCS滝だが、簡単に登れる。それが終わると再び雪田となる。
この雪田では踏み抜きが一回あった。あってもたいしたこと無いはずと想像していても、イザ落ちる瞬間は、例え1mであっても着地して止まるまでの間は、この奈落の底はとてつもなく深いんじゃあないかと不安いっぱいになる。
今回も何ともなかった。
雪田の雪は10cmも潜る状態だし、少し気温が高くなるか、或いは暖かい雨が降るだけでもぐんぐんと融けていくので、もう2月の大雪の痕跡は消えても良いだろうなという季節なのだ。ゴロゴロとした岩の上をヌタヌタと歩くより、雪田の上の方がずっと気分だって良いはずなのだが、沢の中でも特に下に水が流れている部分はとても微妙な状態なのだが、雪田上からは下の状態を見間違い無く見分けるのは難しく、だから上を歩くには覚悟がいる。だが沢の中にはまだ2mを越える厚さの雪が堆積しているところもたくさんある。
小さな雪田の上端が小滝となっていて、その下で雪の縁が崩れた。もう慣れた。
手にしてた杖は滝上に放り上げてから小滝を登る。
次に雪田が途切れたところに10mくらいの高さの涸棚が出る。下部が少しだけ外形したホールドだが、3m登ったところからは乾いた岩でフィット感の良くない靴でも快適に登ることが出来る。
 雪田が急になって細くなって
やがて尾根に上り詰めてバイケイ草の原に入って終わる
雪田が急になって細くなって
やがて尾根に上り詰めてバイケイ草の原に入って終わる
沢は狭く、
浅くなって上部には稜線が感じられるようになる。
振り向いて見て比べれば、丹沢三峰の山頂と同じくらいの高さまできた。山頂は遠くない。そこで雪田が二俣に別れる。
山頂まで行くなら右だが、そうでもなくとも良いとなれば、左の方にこそ雪田が続いていて、こちらの方が右側よりはずっと快適に登って行けそうな気がする。その左側に入ると雪田は百五十mほどでバイケイ草のような草が群生する草原の中に終わる。草原は苔の乗る岩が折り重なる傾斜面の所につながり、そこで沢状が終わる。その苔岩の転がる傾斜面の上端には左に伝っていくような獣道が着いている。それに従って歩く。
上側に鹿柵が見えてきて、ほどなくフイッと登山道に出る。正面には富士山が浮かび、右手に目をやれば蛭ヶ岳山草の屋根がすぐそこだ。二百mは無いだろう。
今日は山頂はなしだ。
鬼ヶ石からランナーが二人下っている。彼等に抜かれた登山者もほどなく二組やってきそうだ。
 沢を抜け出たところから見える富士山
蛭ヶ岳山頂までは二百mはない場所だ
沢を抜け出たところから見える富士山
蛭ヶ岳山頂までは二百mはない場所だ
鬼ヶ石から白馬の尾根を下る。
少し前までは草原にはススキが風になびき、確かに白馬の尾根の風情があった尾根である。
今でもぼんぼりのような馬酔木と笹の原の中央に残っている鉄枠看板立てを見ると、そういう気がしないでもないが、保護すべき樹林が見あたらない草原に、新しく設置された縦横な鹿柵に遮られ、思うとおりに歩くのが難しくなった。それに季節によって彩り変わる夏草よりも、笹の葉が幅を利かせるようになって以前の爽快さが幾分か減じられているように思う。
鹿柵に遮られて、以前のように歩けなくなって、
それは言い訳なのだが、草原中央看板立て付近から、登山道から左に別れて下り出した先に直にあるはずの虎ロープを見つけらなかった。
それでも委細構わず、と下りだしたが、下に本谷沢が大雪渓のように見えるとなると、これは左に寄りすぎた証拠だ。何回かこのパターンで思っているのと違う所を下ってしまった過去がそう言う。
だから左手方向に移動する。厳しい傾斜面ではなく、スリップしても大丈夫そうな山肌中を二百mほど右手方向にトラバースして見慣れた尾根に戻る。そうして本来のコースに入れば、この尾根の植生は明るくて悪くない尾根である。
 白馬の尾根から虎ロープコースで本谷沢(大滝沢分岐より百五十m程奥側)に下降する
この沢はまだまだたくさんの雪で覆われている
白馬の尾根から虎ロープコースで本谷沢(大滝沢分岐より百五十m程奥側)に下降する
この沢はまだまだたくさんの雪で覆われている
尾根末端からは虎ロープを頼りに右手の本谷沢に向かって下る。
下に本谷沢が見え、僅かの時間で下り着くそこの所で古い木の根っこに綱が引っかかっている、その一箇所だけはロープが切れそうだが、それ以外はまだまだ大丈夫で長持ちしそう。
下った本谷川の奥側はいまだ雪渓状だった。でも下側は雪は消えて通常の状態に戻っている。
本谷沢の分岐から沢通しに大滝の滝壺まで行く。青い木々に覆われて滝の周辺はもうすっかり夏の景色である。滝の水量は多く、飛び散って水煙が上がる。太陽の日が当たり若葉と若葉を繋ぐように虹が渡る。そんな大滝落口を下から眺め上げる。
 大滝見物
大滝見物
斜面で着いた汚れを洗うために意識的に水の中を多く歩く。
余計に十歩くらいは川に入る。そうしていると川底の石に滑って転びそうになって慌ててカメラケースの蓋押さえたりする。こうして雷淵上までで靴はすっかり綺麗になった。衣服だって洗濯不要なくらいに戻っている。
 落ちてしまった桟橋(瀬戸沢入り口付近)
登下降には梯子丈が短く腕力も必要だ
見た目よりも登る(特に下る)のが面倒
落ちてしまった桟橋(瀬戸沢入り口付近)
登下降には梯子丈が短く腕力も必要だ
見た目よりも登る(特に下る)のが面倒
 落ちる前の桟橋(2013年)
落ちる前の桟橋(2013年)
水平径路ではこれから大滝だと言う二組・三人と行き会う。桟橋落ちたところで会った人は、5年ぶりに大滝を見に行くと言うが道が圧倒的に悪くなっているとかと嘆いていた。
自宅4:55(自転車で出かける)〜山びこ橋5:50〜魚止橋(自転車止める)6:45〜雷平7:30〜中ノ沢出会い7:40〜乗越沢?合流点9:20〜稜線(蛭ヶ岳に10分程の位置)9:45〜鬼ヶ石9:55〜白馬の尾根10:00〜大滝への道へ10:10〜大滝10:45_55〜雷平11:20〜魚止橋12:00〜宮ヶ瀬〜自宅13:15 20140510 晴れ
頁トップへ マシラのHP
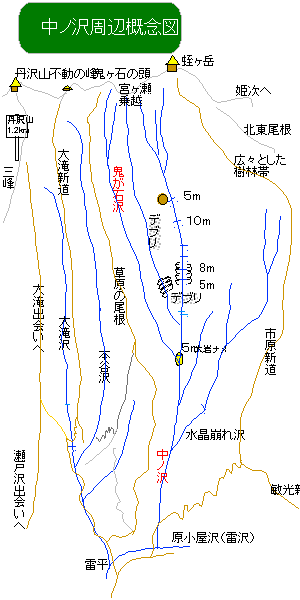 最近、こんなこと考える。
最近、こんなこと考える。










