丹沢 新田沢(堂屋敷沢):葛葉川
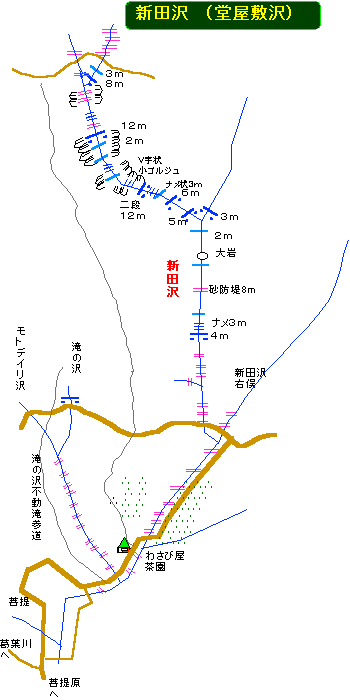
春は花、そして会社では憂鬱な時期。お彼岸の日を迎え、冬が今日で終わった。暖冬だった昨年の今頃には、もう桜は咲き始めていたが、気象庁が言うには今年の冬は平年より寒むかったんだって。「ふ〜ん。そうかな」そうは思えないが
今冬は暮れ前こそ、そこそこ寒かったが、年が明けてからは雪が少なく、雪が積もったら、あの山この山と思い描いていた雪遊びの機会も、結局のところ、しみったれた雪が何回か降っただけだったから、そんな雨雪が凍り固まったツルンツルンの山道は「歩く気がしない」「まともな雪が無い冬の丹沢なんて」と言って、凍った山道を避け続けて終わってしまった。
本当は正月前後の雪歩きに予想外に疲れて懲りて「雪を避けていた」というのが正解だろうとおもう。滝も氷も本凍結しなかった2月の厳冬期が過ぎた頃から、肌寒の日が割合に多かったから平均気温を押し下げて、つまり「平年より寒い」と言う気象庁の総括になるんだろうな。山遊びの体感的に語れば「今年は暖冬」は間違いない。どうでも良いような事にこだわるのは、この時期特有のムシャクシャする憂鬱さを少しでも忘れていたいからだろうな。
北風が背中を押してくれるので、今日の善波トンネルは楽な登りだった。しかし、R246は好きな車道ではない。国道だから車が多いのは当然で、自転車は道路の脇を遠慮しつつ走ればよい。トラックの排気も一時期に比べればだいぶ良くなって来たし、チャリンコに幅寄せするほど暇なトラック野郎は不景気な今のご時世に、いるわけはない。伊勢原から秦野に至る峠道は自転車にはきついが、そんなことは先刻承知だ。
でも、この道は市街地を走る。市街地には当然ながら信号がある。その信号制御は当然ながら車の速度に合わせてあるから、車よりすこし遅い自転車で走ると、大概において赤信号で待たされることになる。
その数が多いから「体が暖まったかな」と思う間もなく、信号に止められる。伊勢原を抜けるまで、これが繰り返されるから調子が上がらない。
思わず、信号無視をしたくなるが、昨日、家の近くで車の途切れた交差点を四方を確認して赤信号を渡って自宅に帰ったら、続いて帰ってきた賢息 (愚息とも言うかな) が
「さっき、そこの信号を赤信号で渡ったのは、お父さんでしょう?」
「僕は見ていた」
「お父さんが信号無視した1秒後に車が走っていて、危うく轢かれるところだった。全くあぶないといったらありゃしない」
「そういう大人サイテイ」と生意気盛りがまくし立てて、高校生の息子に申し開きも出来やしない情けなさだった。
おまけに、今朝まさに、その交差点でハンドルからタンクまでがグシャのバイクと警察官5人、おそらく車の運転手だろう、その脇に茫然と立つ人を見てきてきたばかりだから、もう信号無視はしない。
砂防堤3個までは踏み跡はしっかり、その後はところどころ鮮明、大部分は不鮮明となり、沢には倒木、雑木が覆い被さり、川の石は滑りやすく、入り口部は歩いて快適な沢ではない。
それでも滝が出てくると、やっぱり滝は良いよな。
最初の滝4mは左から小さなつららが下がったホールドを掴んで快適な登りが楽しい。右岸が覆い被さる回廊のようなゴーロを歩き、小ナメ滝と小滝を過ぎると、またまた砂防堤となり、右岸の踏み跡に誘われて藪の道を歩いたが、大岩の堤の上から見れば沢どうしに歩いた方が易しかっただろうな。
次は2m程の小滝である。
左から簡単に越えようと一歩上がったところで、左手のホールドがかけてズルッと水の中に落ちてしまう。足のフリクションが良くないので、そのホールドがないと、この滝は登る気がしない。右の岩の窪に1m程の倒木を立て、右から登りだし、落ち口は先程の倒木の上端を足場にして飛び移るようにして慎重に登る。
右に小滝を支流を水量比3:2で分けて、上流から運ばれてきた廃棄物の残骸の残る沢の中をアチ・コチと渡って歩くと、左手に大岩が被さり、その岩の奥に細く絞って水が流れる5m滝に到着する。大小2本の倒木が列んで立てかけてあり、だれか、この二本を使った登ったのだろうか。でも、僕にはとてもそんなまねは出来そうもなく、右を巻く事になる。
ゴーロは直ぐに次の6m滝につながって、ここら辺りから、滝は次から次に現れるから
「おっ、この沢は思いの外、良い沢じゃん」
と入り口辺りの風情とは一変する事になる。
右から登り、2m上がったところから水の中に一歩足を置いて左に移り、岩のクラックに足を突っ込んで登る。ホールドは良い物があり、快適と言いたいところだが水はまだ詰めたくって、濡れたホールドを掴む手が悴んでしまって、水の暖かさを確かめる程の余裕はありゃしない。
やや狭まった沢の中の簡単な滝を超すと小ゴルジュ。ここには滝も無く簡単な通過だったはずだが、流れの中で石に手を掛けたら50cm程の岩が安定を失って転落した。石で太股を擦っただけだったが、その上の1m程の岩も50cm程はずり落ちて両岸にせき止められて止まったから良かったがこんな石に覆われたらあがらえないな。きっと。股には青く大きな青痣が残ってしまった。
気をつけよう沢歩き
なめるな浮き石
なめよう、甘い汁
続いては2段に重なって見える5m+7mの滝だ。
下は乾いた左から快適な登りが楽しめる。その上の7mは水苔が付き、濡れた順層の流れの左を登るが、ホールドにつららが下がっていて快適とは言いかねる。ホールドが大きく、つららも蹴飛ばせば石に付いた氷ごと落ちるから登れたのは幸いだったが、高度感も下の滝下まで一連となり、ここは登ってはならない場所だった。ムシャクシャスル気分の時には判断もいい加減になるな。
滝の上で沢は狭まり、ザレナメをすぎ、V字状ナメの小滝は足を精一杯開き、それでも足りなくなったら両手と足を突っ張りにして、(「手足が短いけれども芯張り棒には十分役立つ」=ずんぐりむっくりということかな)体に感謝して通過する。
そして、狭い両岸に挟まれた奥に滝が見える。入り口には2m程のCS状小滝があり、その左側を登るのだが、滝の上に出るためのホールドの位置が遠いので、流れの中に一歩足を踏み込まないといけない。ホールドを探している間にズンズンと右足全体が濡れてしまって寒い。手だって充分に悴んでしまっている。気分だけが「コンチクショウ」なんて言ってホールドを探して頑張っている。
この小滝は登ったら、降るのは補助具がないと容易ではないと思う。
続いては公称12m、目測10mの垂直な大滝だ。落ち口の左に楔のように大岩が食い込んでいる。その楔は、まるで閻魔様が、それを打ち込むことによって、この辺りの台地が裂けてせまいゴルジュを作った基点の様な感じだ。当然、この滝はノーザイルでは登れない。しかし、あの入り口は降りれもしないぞ。
でも地獄に仏って言うよね。あるいは渡る世間に鬼はいないとも。
左岸の上方から垂れ下がっていた蔦葛をホールドバランスに使い、3歩上がると砂地斜面の灌木に手が届く。
先程の入り口小滝を飛び降りなくって済んでホッとする。
10m程の砂防堤を右から越えると、粉砕された廃棄物が混じるゴーロ、そのゴーロが一度狭くなると、上に2連の下の堤は右のコンタクトの窪を行き、上は左から不安定な足場を運ぶ捲き道になる。
上に林道が見えると、本流は水が消えて砂防堤になり、右からは8m程の滝が落下する。
8m滝を左から灌木ぶら下がりをして巻き気味に登り、落ち口に着いたら、連続する3mのスラブ滝は流れの中の石粒を拾う細かい登りを行う。真剣になれば手の冷たさも関係なしだが、でも緊張が終わると寒さに手がしびれる。
霜柱の土手を上れば林道に出る。その上方に続く沢は出来たばかりの重なる砂防堤の中に食い入って消えている。
当然、遊びはここまでにする。
草の生えていない時期だったからかな、なかなか良い沢でした。
霞む富士山を遠くに見て、林道が秦野側に突きだすニの塔の全容が見える場所から滝の沢と新田沢の中間尾根を使って「わさび屋茶園」の大きな楠木の立つ場所に降る。尾根には古い材木切り出し道があるが倒木に覆われていて大半歩けず、その脇を歩くことになる。
新田川の道沿いには古く太い桜が何本か立っている。
沢を終えた気安さから、短い上腕を精一杯伸ばして、枝を引き寄せ芽を確認すると、茶色の覆いは1/2は押し広げられていて、その中に萌葱色のつぼみが、次の暖かさのチャンスをうかがって開花するタイミングを図っている様に見えた。
その桜の下の「滝の沢不動の滝参道」を一升瓶持ち、お参りする人達の姿が、もう1週間もすれば見えるだろうか。
今ではそんな優雅な花見をする人はいないかな?
昔、私の爺様は花の季節になると、一人で一升瓶ぶら下げては河原の木の下にござを敷き、温かい日向の下で終日うたた寝していた。沢山の人が話し相手になってくれた時には空っぽの、そうでないときは行くときと変わらない重さの一升瓶を持ち帰宅していた。
私もそんな優雅な花見がもう10年たったら、やりたいな。
出来ることならユミコチャンと一緒に。
(彼女は大の毛虫嫌いだから、桜の木の下なんて、まあ、おそらく、ほとんど、まず、立ち入るなんてこと 無い)
自宅6:00〜菩提:新田地区7:05〜林道〜新田沢アラタ(山屋さんは堂屋敷沢っていうらしいけど、今日は堤に書かれていた名称に統一)7:20〜12m滝8:40〜林道9:15〜滝の沢と新田沢中間尾根〜わさび屋茶園9:45〜自宅10:45 晴れ 2003/3/21
頁トップへ マシラのHP
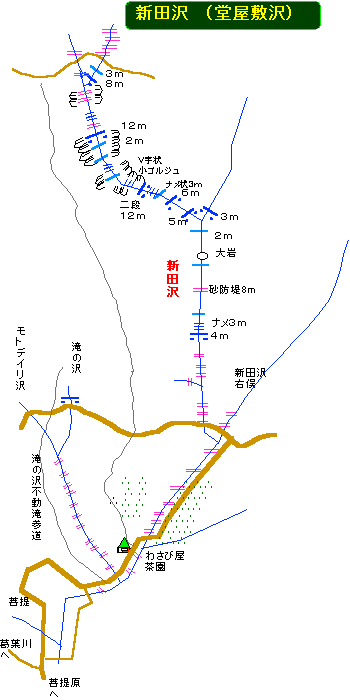 春は花、そして会社では憂鬱な時期。お彼岸の日を迎え、冬が今日で終わった。暖冬だった昨年の今頃には、もう桜は咲き始めていたが、気象庁が言うには今年の冬は平年より寒むかったんだって。「ふ〜ん。そうかな」そうは思えないが
春は花、そして会社では憂鬱な時期。お彼岸の日を迎え、冬が今日で終わった。暖冬だった昨年の今頃には、もう桜は咲き始めていたが、気象庁が言うには今年の冬は平年より寒むかったんだって。「ふ〜ん。そうかな」そうは思えないが


