甲斐駒('96/8/14-15)
甲斐駒('82/8/??)・・・その前に行った甲斐駒
会社は夏休みだというのに新製品関連で連日の出勤。
2階建物のマシンハッチから大山の夕焼けを眺めていたとき、急に山に行きたくなった。
休み明けまで後2日。
それが明けると、又当分忙しい日が続く。
もう仕上がらなければならないのに、量産の目途が立っていない。
歩留まりは驚くべく、低レベルでのたうち回わっている。
どうしたら良いのか分からない状態だ。
明日は山に行こう。
今日、これから山支度をして行ける山。
楽して登れてエンジョイできる山。
そうだ甲斐駒にしよう。
返りのコンビニでポカリスエットを2㍑とラーメンを2袋買った。
かえってユミコちゃんに明日は山に行って来ると言ったら
「ふーん」
ざっくを出し、シュラフカバーとガスコンロとカメラと傘とラーメン、ポカリスエットとポリタンクをいれた。
支度は5分で終了。
朝起きると、お弁当のおにぎりが用意して有った。
自転車で行くには甲斐駒はちょっと遠いので、今日は電車とバスだ。
かっては朝から戸台の河原を歩き、疲れたころ頂上に着く山だった甲斐駒も今は車で行けば、ちょちょいのほい。
とはいっても車のない僕は、朝自宅を出発して新宿、中央線で甲府まで行き、甲府からバス、広河原からマイクロで北沢峠とすると結構時間がかかる。
大勢の人をさばく広河原で小一時間も待たされ、北沢峠に付いたころは、もう昼過ぎだ。
バス停から小屋の前に出て身支度を整える。
2時だ。水を汲む必要はないだろう。
河原を渡り、明るい樹林帯を横ぎり急な樹林帯を歩く。
たいそう元気なおばさんたちの集団がひとかたまり、もうひとかたまりと下ってくる。
石河原に出て甲斐駒の頂が見えてくるころには、誰にも会わなくなった。
六方石をすぎ白ざれた山道をたどる。
夕日が背中にあたる。
今日は黒戸尾根八合目の岩屋と決めて有る。
右から摩利支天の稜線を合わせて暫く行くともうそこは頂上だった。
一人登山者がいて写真をとっていたが、すぐにいなくなった。
祠に座って甲州側を見下ろす。
八ヶ岳を見る。富士山を見る。
青い空の景色だ。
左ルンゼ取り付き 赤石沢奧壁
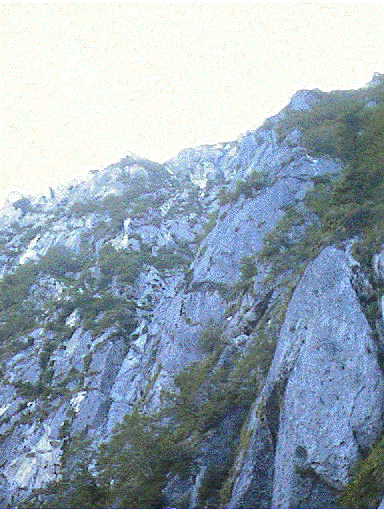 石尾根の黒戸尾根を少し下り、刀を指した石碑を過ぎて、すぐ岩小屋を探す。
確か、この遭難碑があった辺りだったのに、よく分からない。
大きな岩のかげだったはずだ。
ちょっとだけ下ると、鳥居に出くわす。
下りすぎた。戻る。
分かるだろうか。
まぁ見つからなければ天気はいいから、その辺で適当に眠ればいいや。
やはりさっきのとこだった。
ちょっとだけ草で覆われて分かりづらかったが、そこは登山道から、せいぜい5m程のところにある。
前庭付きでゴミもなくきれいに片づいていて、5人はらくらくと横になれる岩小屋に今日は一人だ。
ここは赤石沢奧壁に取り付くバンドにつながっているし、小尾根を下ればそのまま赤石沢A、Bフランケにも行ける。
目の前には大武川のパノラマが広がり、その向こうには富士山が雲に浮かんでいる。
まずは水汲みに行かなくては。
中央綾まで行く。
水がない。
前はここに水があった。
しょうがない、左ルンゼ取り付きまでいく。
昔、来たときは流水溝に水が滴り落ちていて、晴れているのにびちゃびちゃしていた。
でも今日は何処にも水はなかった。
取り付きの岩の窪みにも水はなかった。
そうだ今年は雨が少ないのだ。
まだ1㍑は残っていたポカリスエットで甘ったるいラーメンを作って、大武川、赤石沢が暗くなるのを、じっと見ながら食べた。
星が出る。
シュラフカバーに寝そべってその星をみた。
月のそばの金星がきれいだった。
来て良かった。
石尾根の黒戸尾根を少し下り、刀を指した石碑を過ぎて、すぐ岩小屋を探す。
確か、この遭難碑があった辺りだったのに、よく分からない。
大きな岩のかげだったはずだ。
ちょっとだけ下ると、鳥居に出くわす。
下りすぎた。戻る。
分かるだろうか。
まぁ見つからなければ天気はいいから、その辺で適当に眠ればいいや。
やはりさっきのとこだった。
ちょっとだけ草で覆われて分かりづらかったが、そこは登山道から、せいぜい5m程のところにある。
前庭付きでゴミもなくきれいに片づいていて、5人はらくらくと横になれる岩小屋に今日は一人だ。
ここは赤石沢奧壁に取り付くバンドにつながっているし、小尾根を下ればそのまま赤石沢A、Bフランケにも行ける。
目の前には大武川のパノラマが広がり、その向こうには富士山が雲に浮かんでいる。
まずは水汲みに行かなくては。
中央綾まで行く。
水がない。
前はここに水があった。
しょうがない、左ルンゼ取り付きまでいく。
昔、来たときは流水溝に水が滴り落ちていて、晴れているのにびちゃびちゃしていた。
でも今日は何処にも水はなかった。
取り付きの岩の窪みにも水はなかった。
そうだ今年は雨が少ないのだ。
まだ1㍑は残っていたポカリスエットで甘ったるいラーメンを作って、大武川、赤石沢が暗くなるのを、じっと見ながら食べた。
星が出る。
シュラフカバーに寝そべってその星をみた。
月のそばの金星がきれいだった。
来て良かった。
 次の日3時半に起きる。
頂上に行く。
富士山の左脇から赤みが差し、赤富士になったかと思うと、あっと言う間にいつも見ている青みの深い富士山になり、それから回りの山々にも色が付きだす。
岩小屋まで下り、またまたラーメンを作り食べ、残りカスを燃やしてから黒戸尾根を下る。
七合目の小屋は皇太子殿が宿泊したとか書いてあった。
小屋脇の水場の水を飲む。
うまかった。
今日は下りだけだ。
刃渡りを通り、主のいない5合小屋を見送り、笹平に着く。
横手から帰ろうか、竹宇からにしようか、暫く迷って、まだ通った事のない尾白渓谷竹宇神社の方にする。
そこからバスで帰ろう。
公園になっているそこにはバス発着所はなかった。
しょうがなくて国道20号まで出る。
この間、夏のコンクリート道路は結構厚い。
学校の前まで来たところの公衆電話から妻の実家である逗子に電話する。
次の日3時半に起きる。
頂上に行く。
富士山の左脇から赤みが差し、赤富士になったかと思うと、あっと言う間にいつも見ている青みの深い富士山になり、それから回りの山々にも色が付きだす。
岩小屋まで下り、またまたラーメンを作り食べ、残りカスを燃やしてから黒戸尾根を下る。
七合目の小屋は皇太子殿が宿泊したとか書いてあった。
小屋脇の水場の水を飲む。
うまかった。
今日は下りだけだ。
刃渡りを通り、主のいない5合小屋を見送り、笹平に着く。
横手から帰ろうか、竹宇からにしようか、暫く迷って、まだ通った事のない尾白渓谷竹宇神社の方にする。
そこからバスで帰ろう。
公園になっているそこにはバス発着所はなかった。
しょうがなくて国道20号まで出る。
この間、夏のコンクリート道路は結構厚い。
学校の前まで来たところの公衆電話から妻の実家である逗子に電話する。
そこから、また歩いて横手からの路を合わせるが、バスの時刻表はない。
そうか、この路線は廃止されてバスがないのだ。
白須の集落を通り過ぎ、国道につき、韮崎側に暫く歩くとバスの標識がある。
問題は次の便までにあと2時間以上は待たされる事だ。
それを待っていたら逗子には行けなくなってしまう。
白州町の役場があったのでタクシーの番号を教えてもらい、タクシーで韮崎まで行く。
たった20分ほどだったけど7000円ほどかかった。
間にほとんど信号がない。
すっきりした山行きだった。
よし明日から又仕事しよう。
樹林帯の中にまだらに日が射す。
笹平をだらだらと歩んでいくと、やがて右手からの竹字神社からの道を合わせて急な登りにかかる。
その登り初めの手前で一休みする。
今日の夜にはパートナーであるN君と合う予定になっている。
一休みしている場所の前を一人が通りかかった。
顔を上げてそいつを見るとN君だった。
彼はこちらを見ようともせずに先に行こうとしたのを呼び止めた。
昨年の剣岳の後、山らしいところには行ってなかった。
そういえばその前の山行は2年前の穂高(屏風~前穂~北穂)のP2をMU君と登って以来だったから、かれこれ2年ぶりである。
P2では大きな落石で一本のザイルはまっぷたつだし、残ったザイルも登り切ってチェックしたら芯がきれいに引き裂かれていた。
そしてMU君との山行はそれが最後になってしまった。
長い捜索活動後のこの2年の間に、僕はすっかり現役でなくなってしまったのだ。
ゆっくりと今日の宿泊所である岩小屋を目指す。
翌日は雨だった。
Aフランケで登攀の予定だった。
ここで今晩落ち合うことになっているN、Kの両氏も、この天気ではBフランケを登らずに、ここにエスケープしてくるだろうと考え、待つことにした。
でも彼らは2時間たっても、やって来なかった。
小雨になったこともあり、下のAフランケ取り付きまで行くことにした。
出かけてすぐ又雨は激しくなる。
全身が濡れて、冷たさに身を震わせて下の岩小屋に着く。
そこにいた人に聞くとAフランケをノロノロ登っている二人組がいたと教えてくれた。
岩小屋はそのほかにも人が多く、ゆったりと雨宿りができない。
更に二時間たっても雨は降り止まない。
Aフランケから奧壁への継続はあきらめることにした。
そうと決めると奧壁の岩小屋に戻る。
明日も雨だったら帰る。
岩小屋に帰り着いて先着2パーティ、総勢7人で結構狭くなった。
その中には勤務先競合のC社の人とS社の人がいて、私の相棒はX社だったので、F工業界の話題で大いに盛り上がった晩になる。
こんな場所でふた晩三晩といたら、製品企画関係の話しは筒抜けになってしまうに違いない。
だけど、開発設計だと
程度のたわいない話に終始するんだ。
写真は甲斐駒と関係ありません 1973年 春 栂池
左ルンゼは「岩と雪」のビッグルート100の1番目に載っていたルートで、2年間も登攀をしていない者にとって、十分な圧迫感を持って対峙を迫られた。
中央バンドを10mほど登ったところに残置ハーケンがあり、登はんを開始する。
支持ポイントが有れば躊躇無くランニングを取る。登り始めれば、今までの圧迫感はなくなり、いつもと同じ空白の時間が始まる。
フリーミックス1pは左側に水の滴りのあるところで終わり、2ピッチ目に長屋君がかかる。細かな縦掴みのホールドが30mほどで終わる。
継続していたパーティがなぜか下降を始める。
こちらのピッチが遅いわけではない。
核心部はここから始まる。
ルンゼに入るトラバースは、空中に体が飛び出しそうで高度間がある。
流水のルンゼは体をねじ込むとホールドに手が届かない。
短い足を大股開きに左右のフェースを登れば、左上のビレーポイントに脱せられる。
この上2pは傾斜が徐々にきつくなる狭いクラックに手足を差し込んでの登はんとなる。
良い確保点がないので、びくびくする。
次のピッチは、チョックストーンが今にも落ちてきそうな凹上を左側面から登って、核心部は終わりとなる。
しかしこの上で緊張感は更に高まる。
手に掛けたホールドは力を加えると、ざらざらと欠損しザックが溝にはまって、それが抵抗になって体を上げるのは摩擦に対しての綱引きに勝たないとならない。
確かな確保点は無い。
それでもルンゼから右壁に移って終了点に達する。
更に草付きを15分ほど歩いて、縦走路の傍らに腰をかけ靴を脱ぎ、しびれた足を解放させ緊張は溶けて終わる。
あわせて2時間30分の登はんだった。
後は駆け下るのみ。横手からタクシーに乗って帰る。
頁トップへ マシラのHP
辻まこと
例えば「世界」という単語。そこから普通は、国際情勢とか諸外国のニュースとかいった人間社会の世界のことを考えるらしい。
ところで、わたしはいつもこの単語から、中学生のときに登った甲斐駒ヶ岳、その頂上の眺望に驚いて茫然としたときのことを思い出す。
わたしの視野、わたしの目玉は、それまでこんな広がりを入れたことはなかった。わたしは無限とか永遠といった言葉が見える物だとは想像できなかったと、そのとき思ったものだ。
七合の小屋に泊まって、まだ夜明けにならないうちに起こされたわたしは、眠気の覚めないぼんやりとした頭で頂上にたどり着いた。夏だというのになんと寒いことだろうとふるえている身には、御来光などどうでもいいような気分だった。わたしがおじさんとよんでいた引率者のI氏は、わたしの肩を強くたたいて「しゃんと目を覚ませ」としかった。
東の空がスミレ色に変わってきた。脚下一面、暗い雲海がだんだんわかってきた。空は刻々と微妙に変化し、スミレ色の上空に、とても、この世では二度と見られまいと思うような透明は薄いセルリアン・ブルーが現れた。じっと眺めていると、それはだんだんコバルトに染まっていく。遠い東天に懸かっていた三筋ほどの棚雲が、淡い緑から急速調で濃いオレンジに変化したと思っているうちに、一筋の黄金色のハープの弦が天心に矢になって走った。強いトランペットが耳元で鳴ったかと思った。わたしはいっぺんに眠気が飛び去って、この世界誕生の序曲の前に緊張して佇立した。光の矢は次々と天心を貫き、やがて正視できぬ輝きの中心がせり上がったその瞬間、世界はその光の矢に洗われて、それまでの姿を一変し、闇のエモーションはあとかたもなく消え去った。明るい。ただ明るい青い空気がこともなく天地に満ちて、遠い山並みの間に沈殿していた雲海は、次第に形を崩して刻々とぬぐわれていく。
頂上に立っていた人は十五、六人だったと思った。だれもかれも彫刻のように静止していて、ばんざいを叫ぶものは一人もいなかった。だれもかれも、その大きな感動に縛られていてただ沈黙するのみだった。
わたしは心の中でセカイという言葉を反すうしていた。何度もセカイセカイとくりかえしていた。どんな辞書にもなかった理解がそこにあった。生まれて初めて高い山に登って、こんなすばらしい光景に巡り会った自分は本当に幸福だと思った。
口に出しては言わなかったが、心の中でわたしはI氏に深く感謝した。
山上の景観には人間の世界を越えた認識があるし、単なる自然をも超越した思想があるように、わたしは感じている。
幼い日に、「そこには無限とか永遠といった言葉が見える」と書いた日誌の表現は言葉足らずなものだが、その実感はいまだ死なずわたしの心の中に生きている。
だれだって、自分の視野をこえることなどできはしない。あとは信じることができるかできないかだけだ。しかし山上の景観には、世界という全体でありひとつであるものの存在を信じさせる力があった。
<<出典>>「辻まことの世界」文部省検定済教科書「国語 3」光村図書から
<<筆者>>辻まこと 1913-1975 東京都出身 詩人・画家
頁トップへ マシラのHP
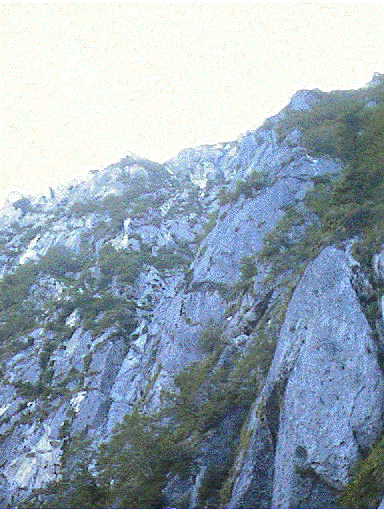
 次の日3時半に起きる。
次の日3時半に起きる。