丹沢 冬のなごりをまぶしさの中に探す。早戸川マゴ沢(左俣)
探せたのは釣り仙人(3人連れ)でしたが、マゴ沢は困難な滝はなく日が射し明るく流れがきれい。
稜線直下まで遡行が楽しめるとっても良い沢であり、期待以上の沢だったと思います。初心者にはお勧めです。滝は無理だなと感じたらすべて簡単に巻くことが可能です。帰りは無理せず、榛の木丸からの稜線をきちんとたどれば伝道、あるいは奥野林道に終点に導いてくれます。
今回は奥野林道からの遡行でしたが早戸川からの遡行もまた楽しみです。こちらを参照して下さい。
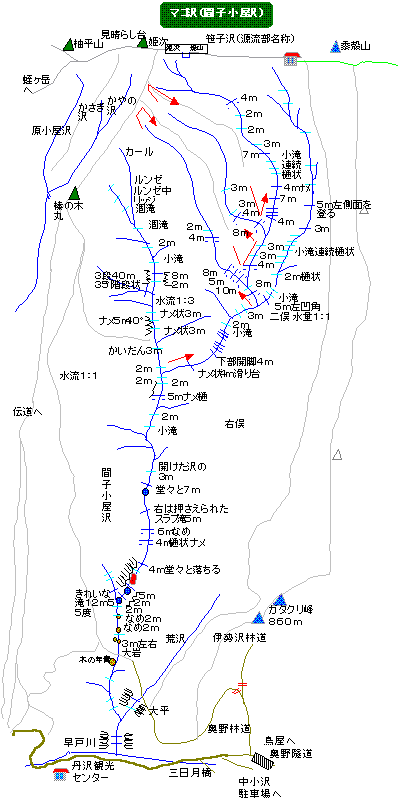 丹沢の谷110ルート、東京雲稜会『丹沢の山と谷』では『マゴ小屋沢』、ブルーガイドでは『マツコウ小屋沢、マツコミ沢』と記載されている沢は現地(奥野林道からマゴ沢に入った所にぽつんと立っている)の猟場案内板では『間子沢』となっています。
今回はこの狩猟案内板のマゴ沢という名称を使わせていただきます。
早戸林道の荒沢出会いにある河川案内図では『マツコウ小屋沢』なっているので、いずれの表記も間違いということもないのでしょう。呼称の違いが生じるのは、多くの人が出入りするか関係しているが、これと言った特徴が少ないことが原因しているのでは無いでしょうか。
今回はともかくもそんな『マゴ沢』に行きました。
前述のような沢ですし、榛の木丸尾根の上から眺めても、なだらかに沢筋が降っていること、ガイドブックにも紹介されていないことからゴロゴロした河原を伝って尾根に至る単純な沢ではないかと想像しました。
だから時間はたっぷりあり、稜線に付いたら原小屋沢の支沢の源流を2,3探ってみようかと思っていました。これは残念ながらアクシデントで取りやめました。
アクシデントというのは自転車です。
もう少しで奥野隧道と言うところで『パーン』と音を立ててパンクしてしまいました。
こんな時のために予備のタイヤを持ってきていますが、ポンプを駐輪場で誰かに取られて無くしていたので、パンク瞬間修理用ボンベを持ってきたのですが、この前鐘沢林道のパンクの時に使った残りだったこともあり、中身が想定より少なく、タイヤの圧が少ししか上がらず、自転車にまたがると地面の”ごと・ごと”がそのまま体に伝わってきて、このまま走ればすぐまたパンク必須でしょう。下りは出来るだけパンクしなかった前輪に体重をかけて後輪を使わず、登りは自転車から降りて引きずっていくことにしました。
おかげで1.5時間もあれば十分にたどり着く予定だった大平に2.5時間もかかってしまい、帰りを考えると、アチコチ歩き回る余裕はなくなってしまいました。全く大ブレーキです。
これでは じじばば 山歩きの世界での『大ブレーク』は夢のまた夢、幻想です。
何を意味しているのか書いている本人も分からなくなってしまい”ゴメン”です。
注意して走ったのですが、やはり帰路、宮ヶ瀬湖畔で完全にパンクしてしまい、タイヤがはずれないか心配しながらの帰宅でした。
丹沢の谷110ルート、東京雲稜会『丹沢の山と谷』では『マゴ小屋沢』、ブルーガイドでは『マツコウ小屋沢、マツコミ沢』と記載されている沢は現地(奥野林道からマゴ沢に入った所にぽつんと立っている)の猟場案内板では『間子沢』となっています。
今回はこの狩猟案内板のマゴ沢という名称を使わせていただきます。
早戸林道の荒沢出会いにある河川案内図では『マツコウ小屋沢』なっているので、いずれの表記も間違いということもないのでしょう。呼称の違いが生じるのは、多くの人が出入りするか関係しているが、これと言った特徴が少ないことが原因しているのでは無いでしょうか。
今回はともかくもそんな『マゴ沢』に行きました。
前述のような沢ですし、榛の木丸尾根の上から眺めても、なだらかに沢筋が降っていること、ガイドブックにも紹介されていないことからゴロゴロした河原を伝って尾根に至る単純な沢ではないかと想像しました。
だから時間はたっぷりあり、稜線に付いたら原小屋沢の支沢の源流を2,3探ってみようかと思っていました。これは残念ながらアクシデントで取りやめました。
アクシデントというのは自転車です。
もう少しで奥野隧道と言うところで『パーン』と音を立ててパンクしてしまいました。
こんな時のために予備のタイヤを持ってきていますが、ポンプを駐輪場で誰かに取られて無くしていたので、パンク瞬間修理用ボンベを持ってきたのですが、この前鐘沢林道のパンクの時に使った残りだったこともあり、中身が想定より少なく、タイヤの圧が少ししか上がらず、自転車にまたがると地面の”ごと・ごと”がそのまま体に伝わってきて、このまま走ればすぐまたパンク必須でしょう。下りは出来るだけパンクしなかった前輪に体重をかけて後輪を使わず、登りは自転車から降りて引きずっていくことにしました。
おかげで1.5時間もあれば十分にたどり着く予定だった大平に2.5時間もかかってしまい、帰りを考えると、アチコチ歩き回る余裕はなくなってしまいました。全く大ブレーキです。
これでは じじばば 山歩きの世界での『大ブレーク』は夢のまた夢、幻想です。
何を意味しているのか書いている本人も分からなくなってしまい”ゴメン”です。
注意して走ったのですが、やはり帰路、宮ヶ瀬湖畔で完全にパンクしてしまい、タイヤがはずれないか心配しながらの帰宅でした。
 奥野林道から見る榛の木丸
奥野林道から見る榛の木丸
ところで奥野林道から分かれる伊勢沢林道は、ちょっと前までは奥まで車が入れたようですが、今回行ってみたら立派なゲートが出来ていて、通行禁止になっていました。無論奥野林道は一般車の進入は出来ません。
奥野林道のゲートをくぐり、自転車を引きずって行くと、途中からダートになります。道すがら見る三峰尾根や本間沢のひだひだ、上部のガレのすさまじい部分まで鮮明です。
目の前に榛の木丸も見えます。マゴ沢の支沢が中間で2条に分かれ山頂に食い込んでいます。早戸川の上流から観ると単なる瘤に過ぎないこの山頂も、こちら側から観ると大きくて見栄えのする山容です。
奥野林道の終点は荒沢の砂防堤です。
ここから横に小尾根を越して石河原、更にもう少し行くと、マゴ沢で前に荒川から来たときに、ここから下流に降っていったところです。古いテープをくぐっていくと、まず左右の大岩で構成する3mの滝になります。左の大岩の上をフリクションで越し、上のナメは流れの中央をフリクションで行くと2mの滝となりますが、垂直に落ちているのでここは越せなくて右を巻いていきます。次の3mは流れの左側のヌルヌルを我慢して越して行きます。イヤなら右側に逃げましょう。入り口からここまで滝を越すのが面倒なときは、右側が広い河原に成っていますので、そちらに良いでしょう。
マゴ沢は源流に行き着くまで、思ったより水量が豊富で、垂直な滝はとうとうと水が落下していて観ていて飽きない沢です。
3mを越すと沢はゴルジュ状になり右側に曲がります。
その曲がり口の左側に支沢が落差12m傾斜度55〜60度位のきれいに落水する滝で合流しています。この滝は中川の『下棚』を少し寝かせたような雰囲気で気持ちの良い棚です。フリクションが利いて中央を快適に遡上することが出来ます。支沢は滝のすぐ上で水が涸れてしまっていて、そんなに上までは続いていないと思います。 大平から砂防堤構築用道路終端まで行って、荒沢を横切りマゴ小屋に入る
大平から砂防堤構築用道路終端まで行って、荒沢を横切りマゴ小屋に入る
 上に細い水流の滝状が見えている
上に細い水流の滝状が見えている
本流に戻るとゴルジュは大きな釜を持った2mとなります。摩擦の利く靴なら右側をフリクションで行けそうですが、つるつるなのと、釜が1.5m以上の深さがありそうなのでここは右側を巻くことにします。巻いた左岸には荒沢方向に延びる集水施設が有ります。まだ使えそうですが今は使われてはいません。多分大平のキャンプ場用として使われてきたのでしょうが、閉鎖になったので後は朽ちるのを待つほか有りません。集水はその上の垂直に落ちる5mの滝の所から行われています。この滝も見た目は大変良い棚ですが、残念ながら集水のためのパイプが散乱しているのは残念です。また垂直なことと深さは1m以上ある大きな釜を持っていて取り付けそうはありません。右側に立派な巻き道(集水施設点検用)が有ります。
 集水用施設用パイプが左岸にある
集水用施設用パイプが左岸にある
ナメを経て、またまた垂直に落ちる4mの滝(写真参照)となりますが、ここは釜が比較的小さく深いので落ちても怪我はしなくてすみそうです。
右側の大岩にスラブが食い込んでいる所を上部のホールドを頼りに上部に抜けると、ここでゴルジュ帯が終わり、広い河原状になります。
小さな滝はこの河原状の部分にも数多く有りますが、滝の部分を登る場合は無理に滝を登っているという雰囲気で河原を歩く方が自然かと思います。
先ほどの4mを終えると、沢はやや左に曲がり鋭く曲がるスラブのナメ状、更にナメ、2段に落ちるナメとなります。ナメの上をぺたぺたとフリクションで行こうとするとツルッと滑ります。流れの脇の部分は水苔ならぬ薄氷が貼っています。一般的にマゴ沢の岩質はフリクションが利きますが、まだ少し冬の名残りがあり、流れの脇は要注意です。流れのしぶきの当たる部分は水温で解けていて凍っていないので困ったときは水の中にホールドを求めるとうまくいきます。
スラブの5mをフリクションで越すと堂々と流れる7mの滝となります。シャワーを浴びるのなら流れの中を行けば易しそうですが、夏でもなく行水は出来ませんので、右側の凹角の大きなホールドをつかんで越していきます。
滝の上部はスラブでつるつるですので、直登する場合は左に逃げる必要がありそうです。落ち口には大きな倒木がちょっと”うざったい”です。
続けて2段の6mです。右側のスラブを登ったけれど、何もそんなところ登らなくってもという感じに右側が開けています。
いったん左に、そして右に曲がり、沢が河原状になり、そこになんと人がいました。
はじめは猿かと思ったんですが、赤いシャツを着た人です。
沢の中で人に会うなんてなんと久しぶりな事でしょうか。
思わず
『こんにちは!!!!』。若いのと(赤いシャツ)と中年の二人の3人連れでしたが、いずれも目つきが鋭く、ひげもじゃ。
まるで仙人のようで、思わずたじろいでしまいましたが、聞くところによると山女目当ての渓流釣りのようでした。風体からしてただ者ではないという雰囲気が紛々と漂ってきます。ともかくも沢の中で人に出会ったのは本当に久しぶりなので嬉しいような恥ずかしいような変な気分です。これからマシラが上に行くことで彼らの釣果に迷惑をかけることは必至でしょうが、そんなものは釣り仙人達の実力からすればどうということ無いでしょう。ごめんこうむって別れました。
右に1:10で小沢が別れ、2mの小滝は大岩のハングで登れず左側スラブを越して行き、左岸側のナメ、2mの小滝を流れの中に入って、更に薄氷の貼った2mのスラブを左側からツルッとしないように注意して、続く2mを右側から越すと、その上の2mとの短い間に右側から沢が合わさります。
二俣
水量比は1:2で左が本流だとは思いますが、右側もなにやら意味ありげに見えていて、黍殻山のあたりに続いているのでしょうか、とてもおもしろそうに思えます。
しばらく行って3mの階段状を登り、右に小さな流れが合流し、対岸の左側には急な尾根が落ちてきています
(この尾根が榛の木丸からの下りで誤って降りてきた尾根です)
広い河原の右隅に水の流れがあって、そこは小さなゴルジュ状になって5m程のナメ滝、3mのナメ、V字状に狭まった3mのナメ滝で、左側面には透明な厚さ1mmほどの薄氷が「ぴっしり」付いています。右側面、及び川面に足をおいて登りますが、なにもこんな所ではなくて、広い河原のどこでも適当に歩いても良いでしょう。
流れの中には至る所に山女の影が横切りますが、釣りに興味のないマシラは、さっきの釣り仙人達のことも忘れて、ひたすら流れに中を突っ走っていきます。
前方に二俣があり、それぞれに大きな棚が見えてきました。左は3段で高さ30m程の滝です。
 何段かの滝 大きいが緩い
何段かの滝 大きいが緩い
右が本流で、こっちも数段で20mは越えていそうに見えます。
水量比は1:3で右が本流です。
まず左ですが、近くに寄ってみると、下2段はなだらかで、どうということもありませんし、上部も傾斜度40度ほどであり、右側から簡単に乗り越すことが出来ます。巻き道も右側にあります。この上では大きな石が沢の中央に横切っていて、後は稜線にガレが押し上げているように見えます。
右に戻りますとナメ、2m、1m程の滝を挟んで8mの3段で構成されている滝です。下部は簡単に越せますが、一番上の段は本来登るんであろう右側にべっとり氷が付いていて登れず、水の流れている部分はシャワーでヌルヌルして登れません。左を巻きます。
 ここはどこだろう?
もう覚えていない
ここはどこだろう?
もう覚えていない
 岩場には氷が残る
岩には薄氷が張る
それがのぼりをきつくする
また、楽しからずや
岩場には氷が残る
岩には薄氷が張る
それがのぼりをきつくする
また、楽しからずや
しばらく間を開けて小滝があり、その先で二俣に分かれます。細いですがどちらにも水の流れがあります。どっちに行っても同じような物ですが、ここでは左に行きます。風にさらされたぺらぺら氷の2mの小滝を越しますが、盛んに水が流れていて、氷も解けて無くなるでしょう。
すでに源流、
ルンゼ状の中に氷に覆われ、ざれた滝が幾つか有りますが、ざれか滝かは明確に区分けは出来ません。
それでも涸滝と思われる部分を2個ほど越し、ガリーの中のリッジを10mほど、ルンゼ状を50m程登ります。枯れ葉の中にまだ解けていない雪の固まりが幾つか有りますが、地面に接している所は全く雪は有りません。
地面から徐々に暖められて雪や氷が溶け、これが流れに連なっているのです。
急な、そしてなだらかなカールをホンの少し行くと、榛の木丸から姫次に向かう尾根に出て、沢の部分は終わります。
雪解けの時期なのか、凍った土が解けだしているのか最後の最後まで水の流れがあり、素晴らしい沢でした。
尾根を暫く姫次に向かい、道界標No392のあたりで左下に日に当たる雪原が目に入り、とっても暖かそうなので、そちらに行くことにしました。
春先の風が当たらない雪原は本当に気持ちがいい。
そのまま左下に数十m程下降して”かさぎ沢”の源流部に入ります。このあたりでは沢と行っても、傾斜はなく静かな窪み状態です。かさぎ沢を更に横切って尾根に上がり、なだらかで 下草の無い樹林帯を”エーデルワイス”法大山岳部 の
『雪は消えねど〜 春はきざしぬ 風はなごみて 日は暖かし〜 氷河のほとりを すべりてゆかば〜 』
なんて歌いながら行くと姫次下ベンチにたどり着きます。
そこには夫婦者の二人がいて、こっちをチラッと眺め、すぐ自分たちの世界に戻っていきました。
ボクは長キジを茂みに撃ちにいった”おっちゃん”と言うところでしょうね。
まだ行ったことのない柚平山まで往復しましたが、山頂は笹藪の中、これはまた風情があって丹沢らしくていい山だと思います。
姫次まで戻ってみると、先ほどの夫婦はこれから降るところです。挨拶の仕方といいボクと同類の人間だな。ありゃ。
今日は時間があったら、地蔵平から地蔵沢を降り、原小屋沢に入り、大滝下の左岸に落ち込む滝を登って再度姫次に戻って黍殻山から大平に帰るつもりでしたが、朝のパンクもあり、以降の予定はショウトカットして榛の木丸から帰ることにします。
榛の木丸からは伝道に行かず、奥野林道に直接降る道のため左手の道をたどり、そこからいくらも降らないうちに踏み跡は更に二つに分かれ、道界標がNo180番台で表示されている左にルートを選んで下ります。
すぐ道が違う事には気が付きましたが、また新しい道を見つけられるからと気にせずに、そのまま降ります。
しかし道は急でもあり、また凍っていた土がまだ解けてもいないので、踏ん張りも聞かずスベルスベル。さっき戻っておけば良かったとちょっとは反省です。
それでも水音が近づき、やがて朝方登ってきた沢に降り立つことになりました。
そこは下部のゴルジュ帯のあたりかと思いきや、上流の大きな二俣のちょっと上のあたりです。やれやれ全くルートファインデングの悪さにはあきれてしまって物も言えません。
それでも知った沢ですので、安全に、安全にあっと言う間に朝の取り付きまで下降して、荒沢から大平を通って帰宅です。
自転車は帰りには完全にパンクしてしまい、これでは家までどれくらい時間がかかることやら。次回には必ず空気詰めを持参しようと反省しきりです。
自宅6:00〜奥野林道ゲート8:00〜荒沢8:25〜マゴ沢8:35〜榛の木丸稜線11:00〜休憩所11:40〜柚平山往復〜休憩所12:10〜榛の木丸12:40〜荒沢(奥野林道終点)13:45〜自宅15:30 2000/03/25
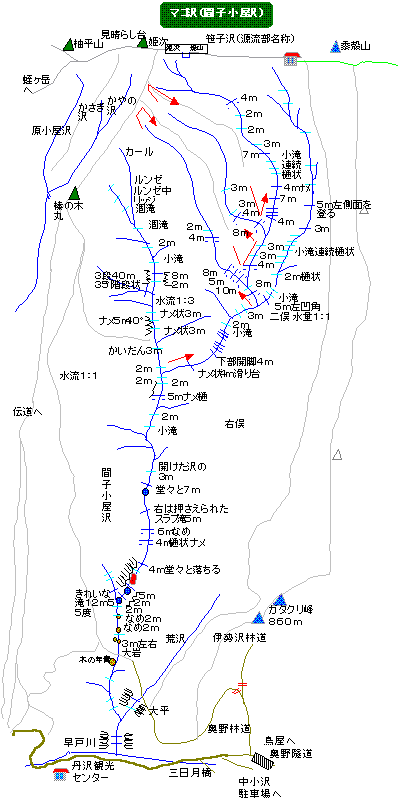 丹沢の谷110ルート、東京雲稜会『丹沢の山と谷』では『マゴ小屋沢』、ブルーガイドでは『マツコウ小屋沢、マツコミ沢』と記載されている沢は現地(奥野林道からマゴ沢に入った所にぽつんと立っている)の猟場案内板では『間子沢』となっています。
丹沢の谷110ルート、東京雲稜会『丹沢の山と谷』では『マゴ小屋沢』、ブルーガイドでは『マツコウ小屋沢、マツコミ沢』と記載されている沢は現地(奥野林道からマゴ沢に入った所にぽつんと立っている)の猟場案内板では『間子沢』となっています。





